ブログが書けなかった私が、ChatGPTに出会った日
「記事を書かなきゃ…」でも手が止まる
「何を書いたらいいか分からない」「文章を始めるのがどうも怖い」 私はブログを始めてから、まさにそんな状態に陥っていました。キーボードを前にして「書こう」と思っても、白い画面と向き合う時間が長くなり、「また明日…」と繰り返す毎日でした。 例えば、「自分の体験を誰かに伝えたい」という気持ちはあったのに、どう構成すればいいか分からない。見出し?導入文?SEO?…と頭がぐるぐるして、文字を打つどころではない。そんな中、ふと目にしたのが「ChatGPTでブログが書けるらしい」という言葉でした。 「AIが書くって…本当に?」という不安と、「もし少しでも楽になれば」という期待。そんな気持ちで、私はチャット画面を開いたのです。
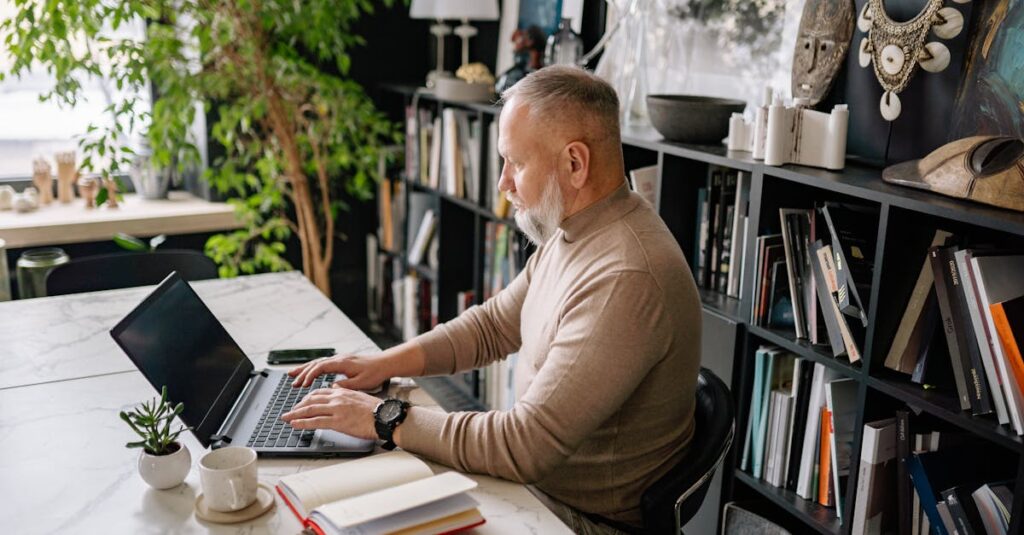
ChatGPTってよく聞くけど、何ができるの?
「ChatGPTって結局、何ができるの?」と調べ始めました。 調べてみると、ChatGPTは文章の構成・見出し作成・下書き生成などをかなりスムーズに手伝ってくれる――という体験談が多く見つかりました。:contentReference[oaicite:1]{index=1} 例えば「ブログ初心者でも構成案が出た」「AIを使って記事を書く手順が短縮された」という内容です。 しかし同時に、「そのまま公開すると機械的な文章になる」「情報が古かったり間違っていたりする」という注意点も出ています。:contentReference[oaicite:2]{index=2} 「使えそうだけど、任せきりにはできないな」という感覚が、直感的に芽生えました。 それでも私は、「まずは試してみよう」と決意しました。何か変わるかもしれない、という期待を胸に。

思い切って使ってみた、そのきっかけ
「今日こそ、テーマを決めて入力してみよう」 そう思ったのはある休日のことです。暇だというわけでもなく、「そろそろ記事が一本も上がっていない」という自分自身に焦りを感じていたからでした。 テーマは「シニアでも安心して始められるAIブログの書き方」。自分にぴったりだと感じたわけです。 まずはチャットを開き、こう入力しました:「シニア初心者向けにブログ記事を書く手順を5つの見出しで作って」――。すると数秒後、見出し案が表示されました。私は「うわ、出た!」と小さく声を上げました。 それが、私の“ChatGPTとのブログ共作”の第一歩です。

最初にやったのは“これだけ”
テキストを打つだけじゃない、試してほしい“たった一つのこと” 私が最初にやったのは、「見出し案をもらう」ことでした。構成が決まると、文章を書くのがずっとラクになります。 ChatGPTが提案してくれたのは5つの見出し。そこから「自分ならこんな言葉を使う」「この部分をもう少し実体験で膨らませよう」と思い、自分用に少し修正しました。 この“小さな一歩”のおかげで、「書き始めた」という実感が湧きました。そして、その感覚が次の“書き続けたい”という気持ちにつながったのです。 今振り返ると、「見出しをもらう」だけでブログを書き始められた――それが大きな突破口でした。

「えっ、ここまで書いてくれるの?」初体験レポ
テーマを決めて一言入力してみた
「よし、試してみよう」と決めてまずやったのが、一言入力でした。 私が選んだテーマは「シニアでも安心!AIでブログを書く方法」。スマホを手に、少し緊張しながらChatGPTに次のように打ち込みました: 「シニア初心者向けに、AIを使ったブログ記事の書き方を5つの見出しで作ってください」 すると、数秒後に画面に見出しの案があっという間に表示されて、思わず「えっ、もう出た!」と声が出ました。 その瞬間、自分がブログを書かなきゃいけないという重荷から解放されたような気持ちになりました。 「一言でこんなに進むの?」…そう思った瞬間、ブログへのハードルがぐっと下がったのです。

見出しも本文もスラスラ出てきた!
見出し案が出た次に、本文のラフ案もお願いしてみました。 「では、それぞれの見出しについて300字ほどで本文案を書いてください」と入力したところ、すぐに各章の文章が生成されました。わずか数分で、見出し+段落がそろった下書きが完成――まさに“魔法みたい”でした。 ただ、画面をよく見ると「少し文章が硬い」「言い回しが統一されすぎているな」という印象も。同時に、「ここを自分の言葉にしたらもっといいな」という気づきが出てきました。 そこで、私は「〜と思います」「私の経験では」など自分らしい表現を入れ替えながら、文章を少しずつ修正しました。 結果、初稿から投稿可能な状態――とはいえ、「AIが作っただけ」では安心できない」という気持ちも芽生えました。

生成された文章を読んで、不思議な違和感を覚えました。 「文章は整ってるけど、どこか“誰かが書いたような”文章だな」と感じたのです。読んでいて、「この言い回し、普段私が使わないな」「もっとこう言いたいな」という部分がいくつも見つかりました。 それはつまり、AIの“賢さ”ゆえに、〈私らしさ〉が欠けていた瞬間でした。そこで私は、「この部分は私の体験を入れよう」「この言葉遣いをゆるくしよう」と少しずつ修正を加えました。 例えば、「スマホ操作が不安だった私だからこそ」と一文を入れたり、「書き終えたときに肩の荷が下りた感じがしました」という実感を添えたり。 その瞬間、見違えるほど文章が「私のもの」に近づいていきました。 AIとの共作は“書き手としての私”を立たせてくれる道具だと実感した瞬間です。

AI下書きを自分でほんの少し手を加えただけで、愛着が湧くブログになりました。 具体的には、思い出話を入れたり、「私も初めて使ったとき、すぐにびっくりしました」などのリアルな一言を加えたり。これにより、文章に温かみが生まれ、「読んでくれている人に話しかけるような感覚」が出てきました。 その結果、文章を見るたびに「これ、私が書いたな」という小さな誇らしさが芽生えました。初めてだったのに、「書き上げた!」という実感がこんなに早く味わえるとは思いませんでした。 また、ブログ公開ボタンをクリックしたあと、「読まれるかどうかより、まずは書いた自分を褒めよう」と思えたのです。 「書けた!」その喜びが、次の記事へのモチベーションになりました。
使ってみて感じた良かった点
「1行目」が出るだけで安心感がすごい。 ブログを書こうとすると、どうしても最初の一文字が出ないことがあります。私も何度も「書こうと思ったけど何も書けず終わった」経験があります。ところが、ChatGPTにプロンプトを入力してから、見出しとともに文章の下書きが出てきた瞬間、頭の中の“白紙の不安”がふっと消えました。 「この見出し下に、こんな内容が書けるんだ」と視覚的に提示されることで、書き始めるハードルが一気に下がったのです。 さらに、構成やタイトルまで提案してもらえたことも助けになりました。自分で一から「テーマ→見出し→文章」と進めると、どこでつまずくか分からず途方に暮れることがあります。私もそうでした。けれど、ChatGPTが「まずはこの見出しで始めましょう」「次にこの内容とこの例を入れましょう」と流れを作ってくれたことで、「書き進められる」という実感が生まれたのです。 また、ネタ切れに悩むことがなくなりました。テーマを頼むと、複数の切り口や関連キーワードも一緒に出てくるため、「今日は何を書こう…」という余計な思考から解放され、記事作成に集中できました。 結果的に、おおよそ半分の時間で記事の雛形が完成し、後は自分の言葉を添えるだけという状態に。これが、私にとって「ブログが楽になる」と感じた大きな理由です。

「書くことに対するハードルが激減」
「何を書けばいいか分からない」→「書き始められる」へ。 ブログを始めた頃、手が止まる瞬間が多かった私。どれだけテーマを考えても、「どう続ける?」という壁にぶつかっていました。ところが、ChatGPTを使ったその日から、テーマを決めてプロンプト入れた後、数分で文章が出来上がる経験をしました。“書いてから修正する”という感覚を初めて味わい、「書くことへの抵抗」が一気に減ったのです。 また、文章量を気にしすぎることもなくなりました。「300字?500字?どうしよう」と頭がぐるぐるすることもありましたが、下書きを提示してもらえると、「あ、これくらいでOKか」と自然と理解できました。時間がかかっていたのは、文章量や構成に迷っていたからだったのだと今は感じます。 “書けない”という諦めが“書ける”という希望に変わった――その変化が、私にとってブログ継続の大きな一歩だったと実感しています。
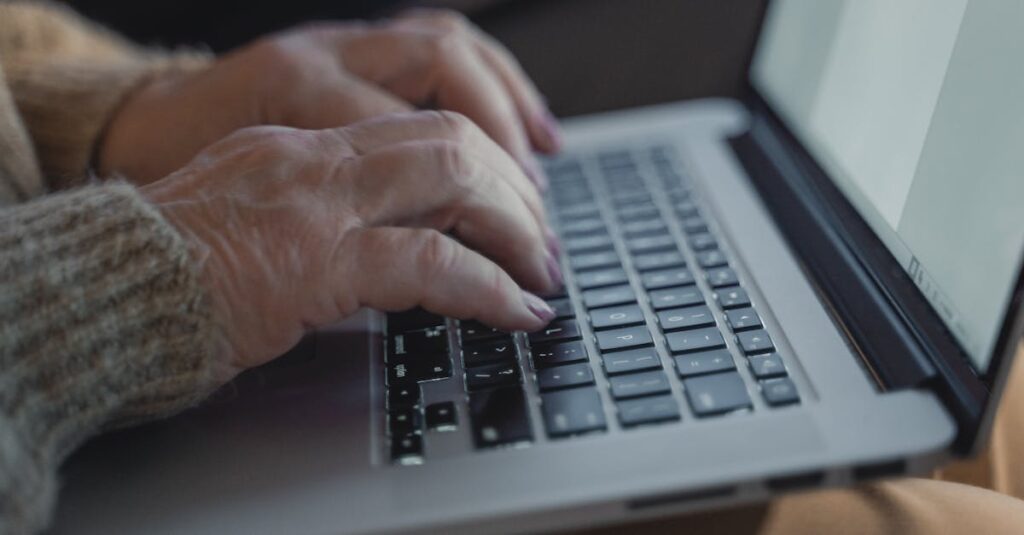
「書けない自分」が「書ける自分」へ
以前の私は、ブログを書こうと思いつつ「書けない自分」にイライラしていました。 「こんな記事でいいのかな?」「読まれるかな?」と不安を抱えながら、何度も途中で止めていました。しかし、ChatGPTで生成された文章に、自分の言葉と体験を少し足しただけで「記事らしく」なっていくのを目の当たりにしました。これを体験したことで、「私にも書けるんだ」という自信が湧いてきたのです。 この“自信”は思った以上に大きな影響をもたらしました。次の記事を書くとき、「また白紙から…」というあの不安が薄れて、「まずはChatGPTで構成を出そう」という考え方が自然と浮かぶようになりました。そうすると、書き始めるまでの時間がぐっと短くなりました。 少しずつではありますが、「記事を出す」という習慣が身につき始め、「書き続けられる自分」が少しずつ育っていきました。

記事の完成率がぐっと上がった!
ブログを始めた頃、投稿までたどり着くのはひと月に1本あるかないかでした。
しかし、ChatGPTを使ってからは「構成 →下書き →手直し →投稿」という流れがスムーズになり、先月は3本投稿できたのです。これは私にとって驚きの進歩でした。
また、構成や下書きをAIが手伝ってくれることで、「投稿できなかった日」の数が明らかに減りました。以前は「今日は気分が乗らないから明日」に延ばすことが多かったのですが、今は「あと少し、下書きだけでも出そう」という気持ちでスマホを開くことが増えました。
結果として、記事の“アウトプット量”も質も、以前より少しだけレベルアップしたと感じます。もちろん完璧ではありませんが、「書けなかった私」が「続けられている私」へ変わった実感があります。

使ってわかった、ちょっとした注意点
「そのまま投稿」はしないほうがいい
AIが生成してくれた文章を、そのまま投稿ボタンを押すのは控えましょう。 私も最初、あまり手直しせずに公開したことがありました。その結果、「読んでいて少し違和感がある」「言い回しが機械的だな」と感じたことがありました。 研究でも、AIツールが「文章を形にする」という点では優れていますが、“読者の心に響く温かさ”や“個人の体験に基づく言葉”の部分では人間の手がまだ必要という指摘があります。:contentReference[oaicite:0]{index=0} そのまま使うと、読んでくれる人に「どこか機械っぽいな」と思われてしまい、せっかくの記事も「味気ない」と感じられることがあります。 ここでのポイントは、AIで作った文章を“あなたの言葉”に変える作業を必ず入れること。修正する・自分の体験を入れる・語りかけの表現に変える――このひと手間が、読者との距離をぐっと縮めます。

「情報が古いことがある」
AIが出した情報、データ、引用が必ず最新・正確とは限りません。 例えば、〈ある調査では〜〉という文章がAIから出たとしても、その出典が明示されていなかったり、実際には存在しなかったりするケースもあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1} 私自身、AIが「2018年のデータでは〜」という文章を出してきたので、「この情報、今でも使っていいのかな?」と調べ直しました。その結果、「この数字、2023年には変わっていた」ということが判明しました。 読者に安心して読んでもらうためには、AIの出力を“事実チェック”する習慣をつけることが大切です。出典を探す、最新データを確認する、自分の言葉で付け加える――これが信頼できるブログ記事になります。

「感情や体験は自分で入れること」
AIはたくさんの文章を学習していますが、あなた自身の「気持ち」「体験」「個性」をそのまま再現するわけではありません。 ですから、文章の中に「私の場合〜」「〜と感じました」というあなたの声や体験を入れることが、記事を“あなたらしく”魅せるコツです。 私の記事にも、「初めてAIにテーマを入力したとき、ちょっとドキドキしました」という一文を加えてみたら、「読み手にとって身近な人の話だ」と感じられたようで、コメントをくれた人もいました。 AIで7〜8割が作れる時代になっても、“1〜2割のあなたの言葉”が記事の印象を大きく変えます。

「AIは『道具』、主役は自分!」
最後に忘れてはいけない大切な考え方です。 AIはブログ記事を“書く”ための強力な道具ですが、文章を届ける相手・読み手を思う気持ち・記事を書く意図――これらは、すべてあなた自身が担う部分です。 私はこのブログ記事を“AIと一緒に書いた”という感覚を持っています。AIが見出しを作り、本文を生成し、私が味付けした――+‑の分担です。 もしAIを「全部任せる存在」と思ってしまうと、読者には「機械が書いた感」が伝わってしまうかもしれません。逆に、「AIが下書きを出してくれて、私はそれをブラッシュアップする」というスタンスなら、記事は自然と“あなたの声”を帯びていきます。 ブログを楽しむ鍵は、AIと“共に書く”こと。主役は、いつだってあなたです。

これからも、ChatGPTと「一緒に書いていこう」
もう「書けない」とは言わせない
「ブログを書きたい。でも書けない…」 この葛藤を何度も味わってきた私にとって、ChatGPTは“書ける自分”へ導いてくれる相棒でした。 テーマが決まらない、書き始められない、文章が続かない――そんな悩みに直面するたび、「とりあえずChatGPTに聞いてみよう」と思えるようになったことが、私の中で一番の変化です。 もう「どうせ無理だ」と諦めなくていい。まずは一言入力するだけで、文章のきっかけが生まれるからです。 “最初の一歩”をサポートしてくれる存在がいる。 それだけで、ブログを書くことがぐっと身近になりました。

少しずつでも慣れていくのが大事
最初から完璧に使いこなそうと思わなくても大丈夫。 私も最初は「どう入力すればいいの?」「これで合ってるの?」と戸惑いながら試しました。 でも、数回使っていくうちに「この順番で入力すればいい」「こう頼めば自然な文章が出る」と、自分なりのやり方がつかめてきました。 ブログを書くたびに、ChatGPTとの“やりとり”のコツが少しずつ身についていくのを実感しています。 「うまく使えるようになるまでが大変」ではなく、「使っているうちに自然と慣れる」 それが、このツールのやさしさです。

「人の言葉」と「AIのヒント」のバランス
ChatGPTを使って気づいたのは、「AIの文章だけでは物足りない」ということ。 逆に、人の手だけで作ると時間もかかり、書くこと自体が負担になる。 そこで私は、「AIの提案を土台にして、自分の言葉で肉付けする」という方法に落ち着きました。 見出しをもらって、本文案を読みながら「私だったらこう言うかな」「この体験を入れてみよう」と編集していく。 この流れが、ちょうど良いバランスなのです。 AI=下書き、自分=リライト。 この組み合わせは、効率とオリジナリティのどちらも満たしてくれます。

「書く楽しさ」を思い出させてくれた相棒
ブログを書いていて、初めて「楽しい」と感じたのはChatGPTを使ったときでした。 「どうしよう」「書けない」という焦りではなく、「この話、誰かに届けたいな」「もっとこう書いたら伝わるかも」と、前向きな気持ちで書けたのです。 これは私にとって、ものすごく大きな発見でした。 AIに頼ることにためらいを感じていた時期もありましたが、今は「AIと一緒なら書ける、続けられる」と思えるようになりました。 書くことは、誰かの役に立つこと。 ChatGPTは、その手助けをそっとしてくれる、頼もしい相棒になってくれました。


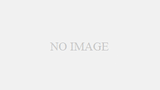
コメント